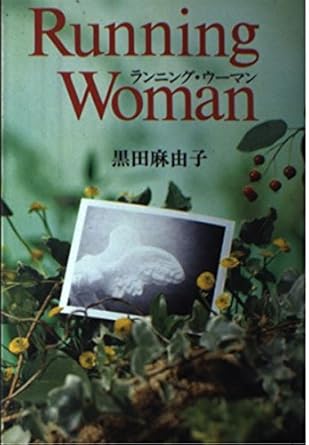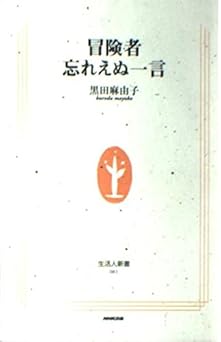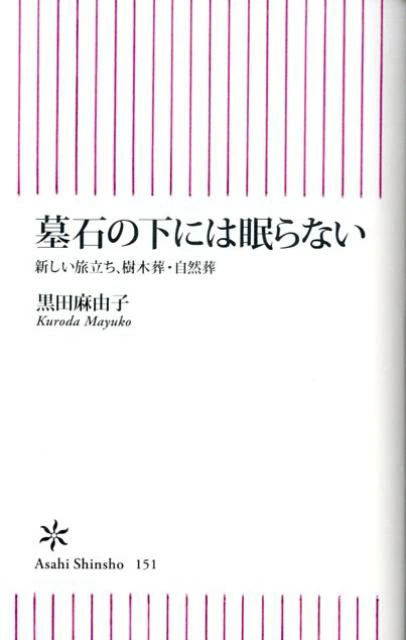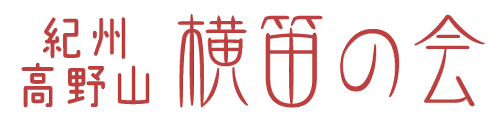妙泉の作家活動について
信者さんからの問いかけにこたえる形で
会員さん:妙泉さんは、僧侶になる前、作家だったんですか?
妙泉:作家というか、ノンフィクションライターという肩書きでライターをしていたんですよ。念入りに取材をしてそれを作品に書き上げるという「調査報道」という分野に近づきたくて、仕事をしていました。
会員さん:そのころの本の著者名は妙泉さんという名前ではないんですよね。
妙泉:そうですね。妙泉というのは、2017年5月に金剛峯寺で得度をした際に、師匠がつけてくださった僧名ですから。いまは何か書くときも僧名で書いています。日本ペンクラブ会員でもありますが、その登録名も「妙泉」としています。ライター時代の商業出版物での筆名は「黒田麻由子」という、わたしの生まれたときの名前で出しています。
会員さん:どんな本を書いていたのですか。
妙泉:「墓石の下には眠らない」「冒険者忘れえぬ一言」「ランニングウーマン」という本が代表作で、ほかにも、インタビューをして書いた本や編集した本など合わせたら20冊以上になるかと思います。また、僧侶になる少し前には、NPO法人でも出版活動をしていました。地域史家などの本を編集したり、自分自身でも書いたりいろいろと取り組みましたね。
会員さん:雑誌のライターでもあったんですよね。
妙泉:そうですね。雑誌の取材記者としての活動はたくさんしていました。21歳から24歳まではとくに、それが主ななりわいとなっていました。
会員さん:25歳で、いまときどき手伝いにきてくれる娘さんがお生まれになったのですよね。
妙泉:はい。子育ても楽しみたいと思っていたので、娘は保育園でなく、真言宗寺院が経営する幼稚園に入園させました。ライターの仕事もできる範囲で続けていましたが、娘が成長するにつれて、また本格的に仕事をしたいと思うようになりました。
会員さん:子育てと仕事を両立させるのは、いつの時代も働く女性の課題ですね。
妙泉:ほんとうにそうですね。そんなご相談にものっていますよ。令和7年に、高野山には女神(弁才天)の部屋、三石不動尊には「姫神社」ができたので、いろんな思いを預けにきていただきたいですね。
関東から高野山に移住するとき
NPOの仲間たちが送別会を開いてくれたのですが、そのとき「麻由子さんは瀬戸内寂聴さんみたいになりたいと思っているわけじゃないんでしょ」と言われました。わたしは、ほんとうにそんなふうに思っていたわけでないので、「寂聴さんは大作家じゃないですか」と笑って「わたしはわたしの道で進みます」というようなことを言いました。
高野山に来て師匠となっていただいた方から、わたしが三石不動尊の住職になったとき、「瀬戸内寂聴みたいになるにはあと20年」などと冗談めかして言われたり、わたしは文章を書くことは好きでしたが、ノンフィクションライターで身を立てていくということは、置いて、高野山に来たのでしたから、sそのときはお寺を再興することに一生懸命、それほどライター活動に未練があったわけではありませんから、「そんなふうにみえるのかなあ」と思ってきました。
お大師さまの息
高野山の高野山ブランド事業に従事して初めての仕事は「お大師さまの息」という本をまとめあげることでした。高野町の産業観光課からの委託の形で取り組み、1年かけて取材して編集した本を出しましたが、このとき、著者名は在家時代の本名の「佐藤麻由子」となっています。高野町役場から無償配布された本です。ちなみに、住職となるときには、戸籍も僧名に変更することに決まっていて、いまは本名は「佐藤妙泉」です。わたしは得度してすぐに「佐藤妙泉」に変えたので、師匠は驚いていました。
僧侶になってから
僧侶になってから、紀州高野山横笛の会の2年目に、全国をまわってワークショップを伝授するというプランがコロナ禍でなくなってしまったことがあり、その間にコンセプトブックを作ろうということで、編集執筆したのが「信じること愛すること」でした。
これは著者名「佐藤妙泉」となっています。
つまり、わたしの本は「黒田麻由子」「佐藤麻由子」「佐藤妙泉」「妙泉」とさまざまな名義で書かれているわけです。
僧侶としてのしごとをするにあたり、過去の作家活動歴はとくに必要ないと思い、かくしていたわけではないのですが、あまり語らずに来ました。
だから妙泉といえば相談・祈祷を行う僧侶であり高野山で横笛の会という密教文化の会を設立した女性であるということが知られていると思いますが、じつはわたしの文筆活動歴はずっと長く、1993年~2015年。23年間ですね。
高野山に来て修行僧から僧侶、住職になるまでが10年ですから、しごととしては前者のほうがずっと長い。過去を捨てたようにして高野山に来たけれど、いまはまた、祈祷の実相のなかで、過去・現在・未来はすべて同じところにあるということを実感しているところです。
そこで瀬戸内寂聴さんのことを思い出して、信者さんからは「寂聴さんも廃寺復興をされましたよね」と寂聴さんの著書をもってきてくださる人もあり、寂聴さんの功績も見直してみたいなと思っている最近です。それは自分自身の作家活動もふたたび表に出てくる契機かもしれません。
代表作のカバー写真を掲載しておきます。
このウェブサイトのプロフィールページに著書一覧もあるので、関心ある方は見てください。
ちなみに、現在、日本ペンクラブに会員として参画しており、その際には「妙泉」という名前で国際委員も務めさせていただいています。