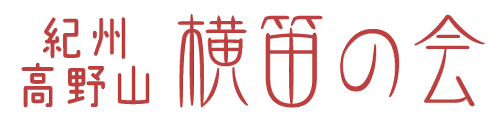祈祷寺での行事
お焚き上げをするべきもの
2月14日三石不動尊でお焚き上げ法要があるので、お焚き上げするべきものを抽出して自室を整理していたところ、初年度令和2年12月に結願した100日祈願の書類などが出てきました。
これは、お申込みになられた信者さまの願いを100日間、わたしが勤行する際に祈念するというものでした。
そのほかにネットで祈願を募集して、拝むというようなことも行っており、創意工夫と試行錯誤のなかで祈祷寺院をつくってきたことがわかります。
願文や次第、信者さまからのお手紙、書籍類も含めて、どうしてもものがたまってきてしまいます。
書類が居室のすみに盛り上がってきますと肝心の休息ができなくなってしまいますね。
今日はたまったもののうち半分くらい、不必要な書類を処分したり、お焚き上げにだすものは精査してまとめて段ボールに入れたりできました。
お焚き上げは都会でできないほかの寺院さんの分も含めて14日11時から三石不動尊境内で行います。
お焚き上げには、護摩札やお札、おまもりのほか、当不動尊では捨てられない人形などの供養もお焚き上げでしたり、小さめの仏像や仏壇などもハッケンしてからご供養します。
思い出の靴だとか、本だとかを出す人もあります。
お焚き上げの効用
過去現在未来というのは同じ場所にあるというのは何度かこのブログでも述べています。
過去のものをいかに供養するかということは、現在をよりよくすることにつながります。
過去にたいせつにしていたもの、過去を護ってくれたものを丁重に感謝してご供養することで、現在の指針がより太くなります。そして現在から続いていくものが未来ですから、この未来の裾野になり、豊穣にしていくことになります。
はやりの断捨離というのとはまた違います。
「捨てられないたいせつなもの」を仏道に則って供養するということは、使わなくなったものを積極的に捨てていくということとは次元が違うのです。
お焚き上げをすると、時空間をこえて、出会いと分かれが交錯することがわかります。
だから最初のころは、わたしはとても悲しい気持ちになっていました。喪失感が私の胸をさすようにして上がっていきました。
それは、この寺院が閉じていたころ眠っていたものが成仏していく過程だったといえるでしょう。
さいきんは、それほどでもありませんが、お焚き上げ法要のあとは境内がすっきりとしています。
上がりたい御霊が、不動瀧を通じて上がっていくからだと思います。
令和7年の7月になにかが起こりますという声は
このころまでに、これまでの自分自身についたよぶんなものを落としていくこと
さらに、新しい時代に対応できるような自分になるためには、
いちばんたいせつなのは自分を許せるようになることなのです。
国難や天災がおこるかどうかというよりも、いやそれの可否にも密接につながってくるでしょうけれども
人間ひとりひとりが自分自身の罪穢れを受け止めて自分で流していけるかどうかということが問われています。
なぜならそれは過去の無念と密接につながっており、いま、現在生きている人間が懺悔ができてこそ、明るい未来が開けていくからです。
これは実際、過去現在未来の法則を知ったら、だれにもわかってくるはずです。
だからまだいまだに人を貶めることや悪だくみや悪意や悪事に染まっている人たちは、いつまでも修羅のなかに。
それに気づいて等身大の自分自身をみとめてあらたに歩いていこうとする人は明るい光がさしてきます。もちろん人生はどんなときにも、浮き沈みがあり、喜びがあれば試練もあります。
しかし生きるステージ(仏道では悉地)が違ってくるということなのです。
亡くなった方々もさまざまな段階があります。
慰霊祭は過去現在未来が溶け合う魂の儀式です。